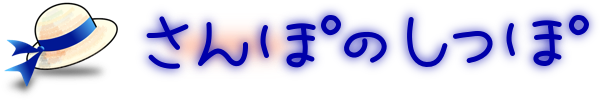チェルノブイリを見にゆく話その19。前回その18はこちら。



旧ソ連軍の大陸間弾道ミサイル早期警戒システムの廃墟ドガ。レーダーは当時のまま、いまもそこにあったが、錆びついてうち捨てられていた。ひとが住まなくなった団地に残された超巨大なジャングルジムのようだった。その背後に建つ旧コントロームルームを見たあと、さらに構内を歩きまわる。構内は、廃墟につぐ廃墟だ。


また別の部屋に入った。ミサイルの絵の描かれたパネルが何枚も壁に掲げられていた。教卓みたいな場所もある。教室のような造りだ。一般のビジターに向けられた展示であるようにおもわれた。G氏に確認してみた。やはりそうだと言う。冷戦下の旧ソ連、当時どんなひとがどんな目的で「ビジター」としてここを訪れたのだろうか。








外へ出た。しばらくゆくと、屋根の下に、すっかり赤く錆びついたポンプがおかれていた。オランダ組のRは職人でNは軍人。そのためか、この種の装置のことに詳しいらしい。かれらが少しいじると、圧縮をかけるらしいピストンの部分が前後に動きはじめた。かつては消防施設だったのだろうか。






その近くに円筒形の構造物があった。G氏がぼくたちに向かって、まあ見てろと手振りで示し、すかさず小石を窓から投げ入れた。ボチャンと音がする——のかなとおもっていると、なかなか音がしない。ようやくポチャンと音がしたのは、予想よりもずっと長い時間がたってからだった。


G氏いわく、井戸というよりは貯水槽のようなものだったのではないか、正確な用途はよくわからんが、とのこと。もしかすると冷却用だったのかもしれないと、ぼくは考えた。これだけバカでっかいレーダー装置やコンピューターは、猛烈に発熱したはずだ。空冷ではとても追いつかない。じっさい真空管にも水冷式は存在した。


G氏につれられて構内を歩く。どんどん歩いてゆくと、小径のまんなかに、ちいさな松の幼木が生えていた。「なんだか平和の象徴、みたいだ」とぼくが言うと、Mが「希望ね」と言った。


むろん、言ってみただけだ。そうだといいとはおもうが、所詮はマックシェイクみたいに甘ったるい話である。そういう類いのことを気安く語りたければ、眼前の現実から目をそむけることが不可欠であろう。
構内はほとんど森と化している。ぼくたちの目には森にしか見えなかった。だが、おそらく当時の構内は整然としていたのだろう。放棄・放置されたあと、木々が勝手に生えてきて、いまや森化しているのだ。『風の谷のナウシカ』の腐海のように。


昨日のプリピャチでもそうだったが、ここでもあちこちにリンゴやプラムの木があり、ちいさな実をつけていた。G氏やNやRは、ときどきそれを採って囓った。


木々のあいだを、時に藪漕ぎしながら抜けてゆく。するとふいに、半ば朽ちかけ埋もれた建物に出くわす。そのくりかえし。










2時間かそれ以上歩きまわっただろうか。最後にエントランスのところへ戻ってきた。


ここに簡易トイレが数基ならんでいた。工事現場においてあるような、PE(ポリエチレン)かなにかでつくられた仮設のものだ。そのひとつにぼくが入ろうとすると、G氏に、「息を吸わず吐かずに行け」と言われた。なにかの冗談なのかとおもった。だが、そうではなかった。
簡易トイレのなかは、具体的に描写したくないほど、ひどい状態だった。なるべくなにも考えないようにして用を足し、外へ出た。オランダ組の二人は「草むらでしよう」と言って、つれだって消えた。


Mに「トイレのなかはどうだった?」と訊かれた。「地獄よりはマシかも」とぼくが答えた。するとMは「あたしも草むらにするわ」と言って、オランダ組とは別の方角を、だいぶ奥のほうへ歩いていった。
その20へつづく。