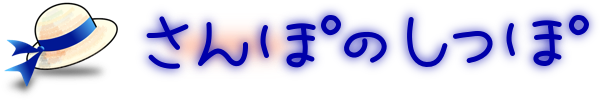世界でもっとも過酷な道のひとつ、ダルトン・ハイウェイを走破する旅その25。北極海に面した街プルドーベイは油田のための人工的な街だった。その大部分は石油会社の私有地だ。ぼくはうっかりまちがえてその民有地内に入り込んでしまい、警備員につかまってしまった。さいわい事情はすぐに理解してもらえたものの、いちおう詰所までつれていかれることになった。

パトカーみたいな警備車輌が先導するので、ついて来いという。二人の警備員のうちのひとりがユーコンXLに同乗した。
助手席にすわった警備員は、見たところ40歳くらいだろうか。じつは昔海軍で潜水艦に乗っていて、佐世保に三年いたことがあるという。
「少しだけど日本語もできるんだ」というから、どんな言葉を知っているのかを訊いてみた。すると、いかにも英語圏のひとの片言の日本語といった発音で、「こんにちは」「ありがとう」「ビールください」と口にしてみせた。
「なんだ、ぼくのスペイン語と同じだ」といって、ふたりでちょっと笑った。
「あなたはサブマリナー(潜水艦乗り)だったというのなら、エリートだったんだね」とぼくがいう。警備員は、一瞬まをおいてから、「イエス」と答えた。ちょっとうれしそうだった。
とはいえ、退役後にアラスカの果ての果てで、日曜日にうっかり敷地に入り込んだまぬけな東洋人をつかまえたりしているというのは、元海軍のエリート軍人の転身先としてどうなのだろうか。


詰所に着いた。狭い詰所のなかに、ぼくと、クルマでやってきてぼくを拘束した二人と、さらにそのほかの警備員たちが入り込み、すし詰め状態となった。警備員たちはガタイも大きいので、余計に場所をくう。
身分証明書一式の提出を求められたので、運転免許証(ミシガン州発行のもの)とパスポートを見せる。それらは一式すべてコピーをとられた。
「どこから来た?」とあらためて訊かれた。「ミシガン州アナーバーから」と答える。たいていのアメリカ人がそうするように、やはり「アナーバー? じゃあ大学のプロフェッサーなのか?」と重ねて訊かれたので、そうだと答えた。
端末で身分照会らしきことをしているあいだに、佐世保の警備員が、北極海を見にいきたかったのか? それならデッドホースのツアー会社(これも石油メジャーの関連会社なのだろう)に頼めばつれていってくれる、と教えてくれた。
べつにそこまでして北極海を見たかったわけではないし、そのためにこんなところに泊まるつもりもないので、ありがたくお断りした。代わりに、ダルトン・ハイウェイの終点の場所を教えてもらう。ついでに、ガソリンスタンドの場所も。
その26へつづく。